北海道民は牛肉を食べない?実は“豚肉文化”が根付く食習慣
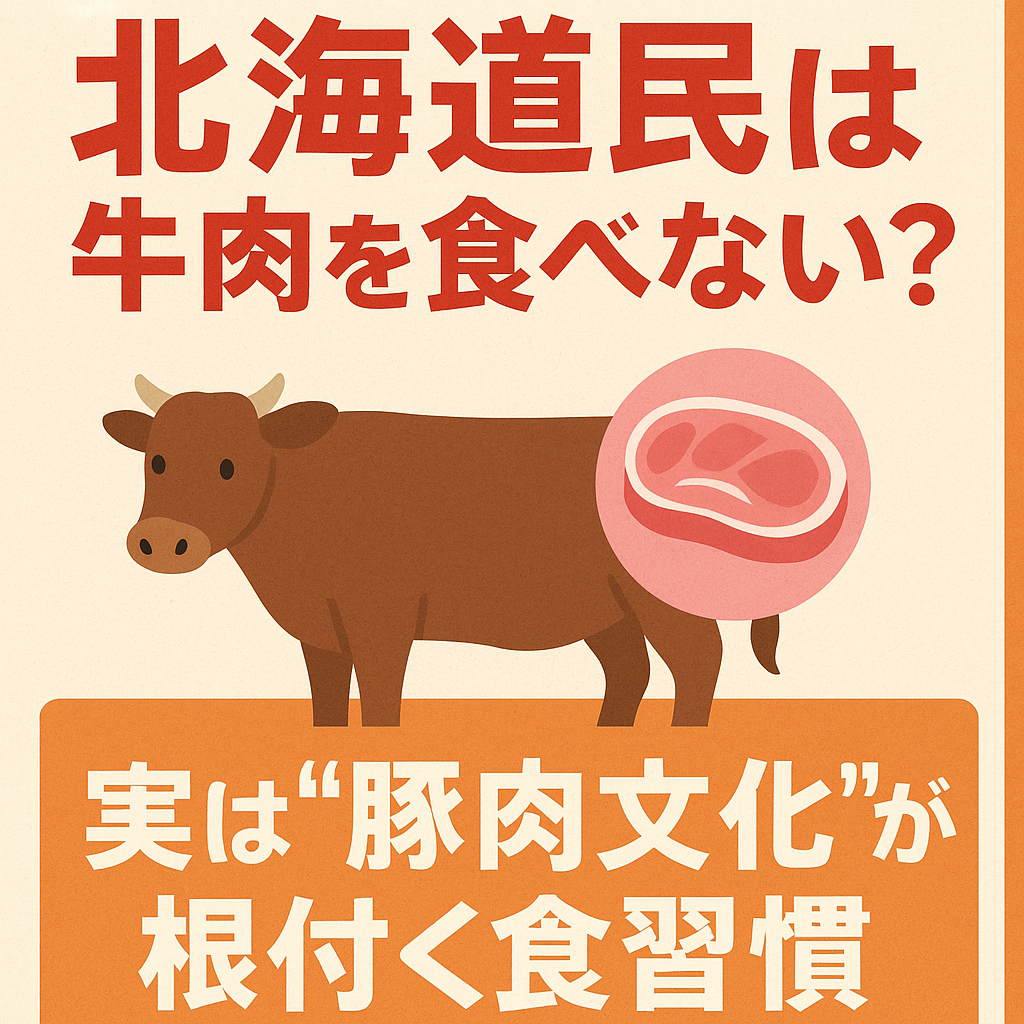
北海道といえば、広大な大地と乳牛が放牧される風景が象徴的で、全国の酪農業の大半を担っている地域です。
そのため「北海道=牛=牛肉」というイメージを持つ人は多いでしょう。
しかし実際のところ、北海道民の食卓では 牛肉よりも豚肉を選ぶ傾向 が強く、「北海道民は牛肉を食べない?」と感じるほど豚肉文化が根付いています。
スーパーの精肉売場でも豚肉の占める割合は大きく、家庭料理や外食でも豚肉が主役になる場面が多いのです。
そこで今回は北海道民はなぜ牛肉を食べないのか、北海道民である筆者の体験談も踏まえて解説していきます。
この記事でわかること
- ✅ 北海道民が牛肉よりも豚肉を好むといわれる理由
- ✅ 道民に根付く“豚肉文化”の具体例(豚丼・室蘭やきとり・味噌ラーメンなど)
- ✅ 畜産農家でも「牛を育てるが豚を食べる」傾向がある実態
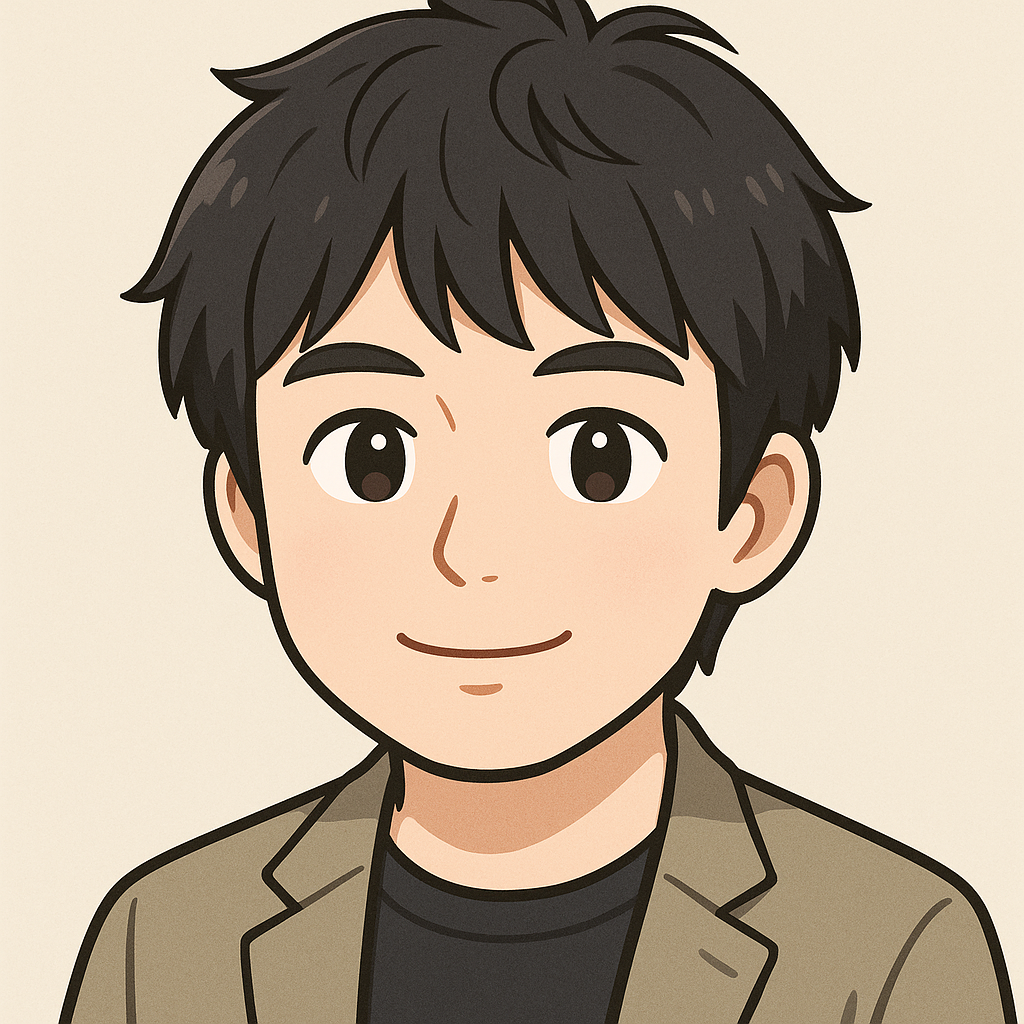
この記事の監修者:うしまる
北海道の元農協職員。15年以上、肉用牛農家の経営支援
ファイナンス設計・新規事業立ち上げを経験。
現在は「牛肉会」の編集長として、科学的かつ実務に基づいた牛肉情報を発信中。
北海道民が牛より豚を好む理由
① 豚肉の消費量が日本一圧倒的に多い
総務省の家計調査によると、日本全国の二人以上世帯における年間平均豚肉消費量は約19,564g。牛肉(6,567g)の約3倍という結果です。そしてこの豚肉消費量が最も多いのは 北海道で23,171g でした。
参考:Jタウンネット|都道府県別統計とランキングで見る県民性
→ 日常的に豚肉を多く食べていることが数字として裏付けられています。
② 牛肉消費は全国平均より低く、スーパーの品揃えにも反映
札幌市では、生鮮肉の年間消費量は全国平均とほぼ同じ5万gほどですが、そのうち 牛肉はわずか8.8%(約4,500g)。全国順位は46位と低く、代わりに豚肉や鶏肉の消費が多い傾向にあります。
参考:Agenda note (アジェンダノート)
地元スーパー「DZマート」の品揃えでは牛肉が少なく、「牛肉は頻繁に食べるものではない。豚・鶏さえあれば困らない」という消費者の声も聞かれます。
参考:Agenda note (アジェンダノート)
→ 消費の現実が、流通や販売にも強く反映されているのです。
③ 歴史的・風土的背景で豚肉文化が根強い
北海道では開拓時代から豚肉が好まれてきた歴史があり、養豚業自体も盛んです。現在では飼養頭数は全国第3位の約72.8万頭(2022年時点)。
参考:PREZO(プレゾ)|ホクレン公式サイト
北海道の冷涼な気候は豚にとって快適であり、病気や環境ストレスが少なく、より安全・安心な肉として親しまれる土壌があります。
参考:ホクレン公式サイト
→ 歴史・気候・生産体制が三位一体となり、豚肉文化が根付きやすい構造です。
④ 豚肉を使った家庭料理や郷土料理が豊富
北海道では、すき焼きも一般家庭では 牛ではなく豚肉を使うことが多い という文化があります。Jタウンネットのアンケートでは、北海道のみ豚肉派が55.2%と牛肉派を上回る結果でした。
参考:ホクレン公式サイト|Jタウンネット|7cascadesブログ
また、家庭料理の定番であるカレーや肉じゃがにも、豚肉を使うケースが多く、地域文化として根付いています。
参考:Jタウンネット|7cascadesブログ
→ 生活の味覚に深く定着しているがゆえ、他地域とは異なる肉の感覚があるのです。
まとめ
| 要因 | 具体内容 |
|---|---|
| ① 豚肉の消費量が圧倒的 | 全国トップの豚肉消費量(23,171g)で牛肉の約3倍 |
| ② 牛肉消費は低め、流通にも反映 | 札幌市での牛肉消費8.8%、スーパーも品揃え少なめ |
| ③ 歴史的・気候的背景 | 開拓時代からの養豚文化、冷涼な気候による飼育適性 |
| ④ 郷土料理への定着 | すき焼きやカレーなど、家庭料理でも豚が主役 |
北海道の“豚肉文化”の代表例
北海道では上述の通り、牛肉ではなく豚肉を食べるのがメインとなっています。
北海道の豚肉文化を代表するように下記のようなレシピが有名です。
十勝豚丼(帯広)
帯広発祥のソウルフード。厚切りの豚ロースやバラを甘辛ダレに絡め、香ばしく焼いて丼飯にオン。炭火の香りが特徴で、観光客にも定番。
- 主に:ロース/バラ
- 味付け:醤油・砂糖・みりん・酒
- 食べ方:仕上げに追いダレで照りを出す
室蘭やきとり(実は豚肉)
「やきとり」と呼びながら豚肩ロースと玉ねぎを串に。タレ or 塩で、からしを添えるのが“室蘭流”。居酒屋文化に根付いた庶民の味。
- 主に:肩ロース
- 味付け:タレ/塩+和からし
- 食べ方:玉ねぎの甘みと豚のコクを一緒に
札幌味噌ラーメン × 豚チャーシュー
コクのある味噌スープに、豚バラ/肩ロースのチャーシュー。ラードで炒めた野菜と相性抜群で、「北海道=豚」の日常感を象徴。
- 主に:バラ/肩ロース
- 味付け:醤油ベースの煮豚/焼豚
- 食べ方:スープに軽く浸して旨みアップ
豚汁(寒冷地のごちそう)
冬場は家庭や学校行事で大活躍。豚こま肉に、じゃがいも・玉ねぎ・にんじん・ごぼう。味噌と出汁で体の芯から温まる“道民スープ”。
- 主に:豚こま/切り落とし
- 味付け:だし+味噌(白・合わせ)
- 食べ方:仕上げに長ねぎ・七味で香りづけ
豚の味噌漬け/生姜焼き(道産玉ねぎ)
スーパーの惣菜や家庭の定番。
畜産農家の意外なリアル
北海道は全国でも有数の畜産王国であり、牛の飼育頭数は全国トップクラスを誇ります。農林水産省の統計(2023年)によれば、全国の牛の飼養頭数はおよそ385万頭。
そのうち約123万頭が北海道で飼育されており、全国シェアは30%以上に達しています。
特に乳牛に関しては圧倒的で、全国の乳牛約133万頭のうち約82万頭(シェア60%超)が北海道で飼育されています。
また、肉牛(肉用牛)においても約41万頭と全国1位であり、黒毛和牛の肥育農家や交雑牛(F1)の生産も盛んに行われています。
しかし実際に農家の食卓をのぞいてみると、必ずしも牛肉が主役ではありません。むしろ「育てる牛は売るもの」「食べるのは豚肉」という家庭が多く見られます。牛は出荷して収入につなげる家畜であり、日常的に食卓に並ぶものではないのです。
筆者がこれまで交流してきた農家の方々からも、次のような声が聞かれました。
- 「焼肉は牛よりも豚が多い。コスパがいいし、家族みんなが好きだから」
- 「牛肉はお祭りやお盆などのイベントや、贈答用として食べることが多い」
- 「毎日育てている牛を食べるという感覚はあまりない」
つまり、畜産農家だからといって牛肉を日常的に食べているわけではなく、むしろ庶民的で手に入りやすい豚肉の方が食生活に深く根付いているのです。
この事実は、北海道に根強い“豚肉文化”をさらに裏付けるものだといえるでしょう。
実際に筆者も今でこそ仕事柄牛肉を良く食べますが、元々はほとんど豚肉・鶏肉でした。
牛肉よりも安いし、買いやすいですし、そもそもスーパーに牛肉は少ないといったのが主な理由です。
とはいえ、味はやはり牛肉の方が美味しいと感じますし、ごちそうといえば牛肉というイメージは昔からありました。
まとめ|北海道民が牛肉よりも豚肉を食べる理由
- ✔ 消費量の違い:
北海道は年間23,171gの豚肉消費量で全国トップ、牛肉の約3倍という数字からも“豚文化”の強さがわかります。 - ✔ 牛肉は特別な存在:
牛肉はスーパーでも品揃えが少なく、お祭りや贈答用のごちそうとして位置づけられています。 - ✔ 歴史と気候:
開拓時代からの養豚文化と、冷涼な気候による豚に適した飼育環境が豚肉人気を後押ししています。 - ✔ 郷土料理の定着:
豚丼・室蘭やきとり・味噌ラーメン・豚汁など、家庭や外食でも豚肉料理が定番となっています。 - ✔ 農家のリアル:
畜産農家でさえ「育てる牛は売るもの、食べるのは豚」と語り、筆者自身もかつては豚肉中心の食生活でした。
あなたにぴったりの牛肉がわかる「LINE診断」
「どの部位を選べばいいか分からない…」「贈り物にぴったりなお肉を知りたい!」
そんな方のために、牛肉会ではLINE限定の
かんたん診断コンテンツをご用意しました。
簡単な質問に答えるだけで、 あなたに合ったおすすめの牛肉が分かります。
- 自分や家族の「好み」に合わせて最適な部位を提案
- 「焼肉・すき焼き・ステーキ」など用途別にも診断OK
- 所要時間は30秒ほど、すぐに結果が届く
※友だち追加後すぐに診断できます。




