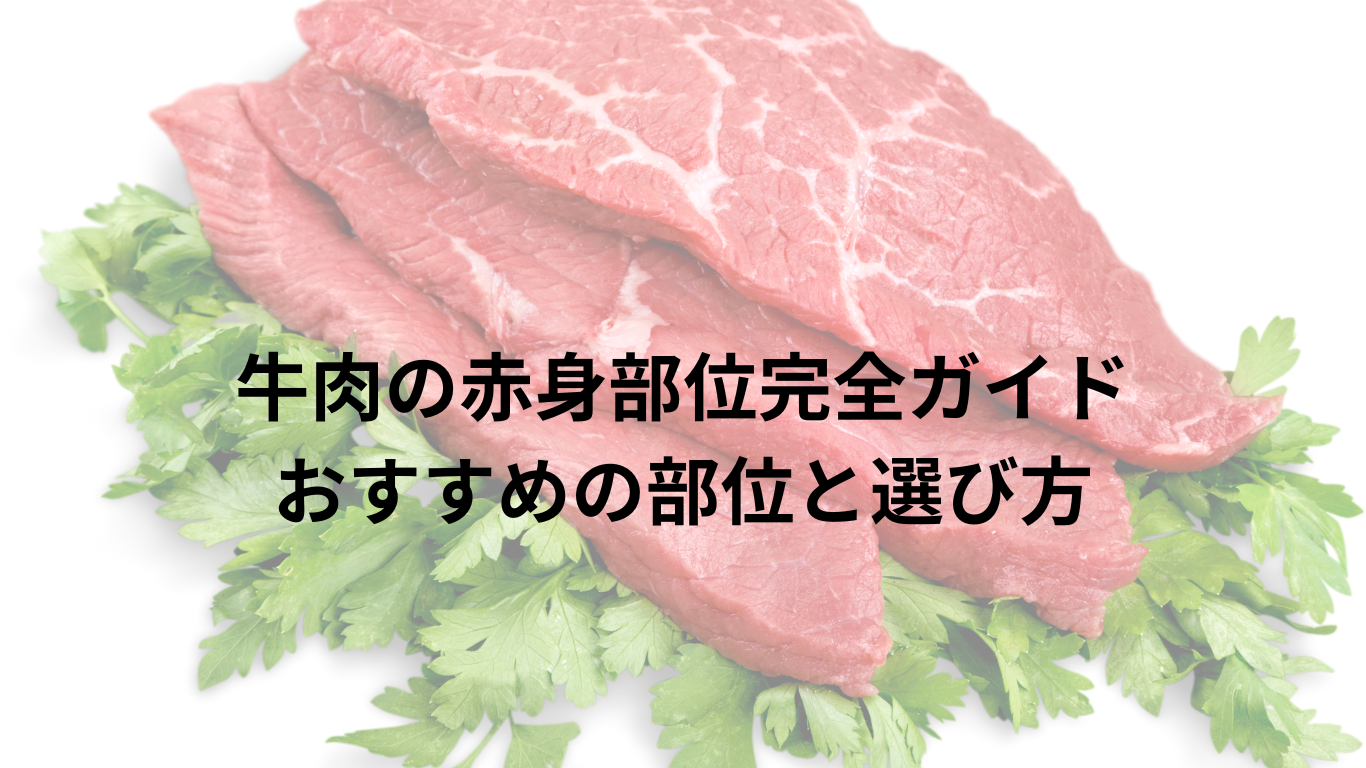ハラミは脂が多い?カロリー・栄養価・美味しく食べるコツを解説!
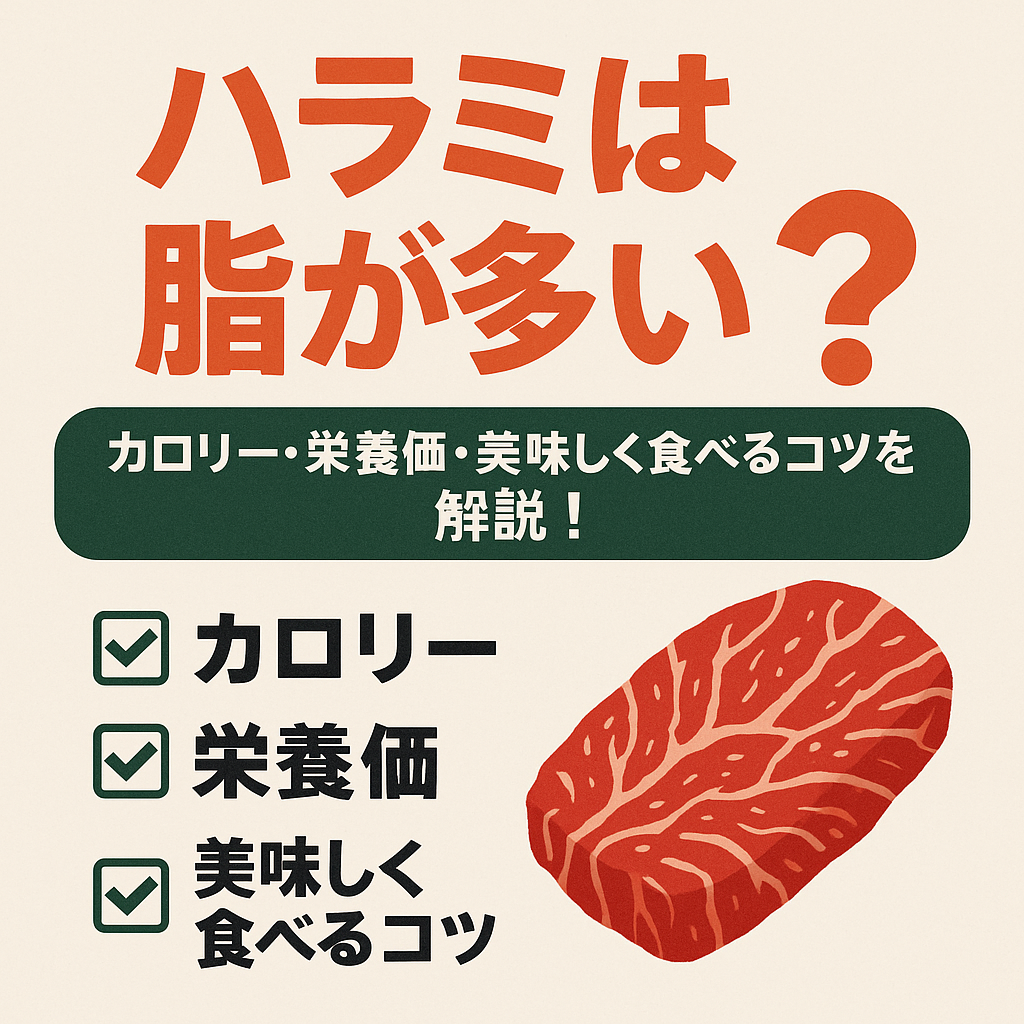
焼肉で定番の人気部位「ハラミ」。見た目は赤身に近く「ヘルシーな部位」と思われがちですが、「実は脂が多いのでは?」と感じる方も少なくありません。
実際にハラミは独特のジューシーさがあり、脂の旨味が美味しさを引き立てています。
本記事では、ハラミの脂質量・カロリー・栄養価を科学的なデータに基づいて解説し、さらに脂を活かした美味しい食べ方や、ダイエット中でも上手に楽しむための工夫について紹介します。
この記事でわかること
- ✅ ハラミの脂は本当に多いのか?科学的データで解説
- ✅ カルビやロースとの脂質量・カロリー比較
- ✅ 脂を活かした美味しい焼き方のコツ
- ✅ ダイエット中でも安心して食べる工夫
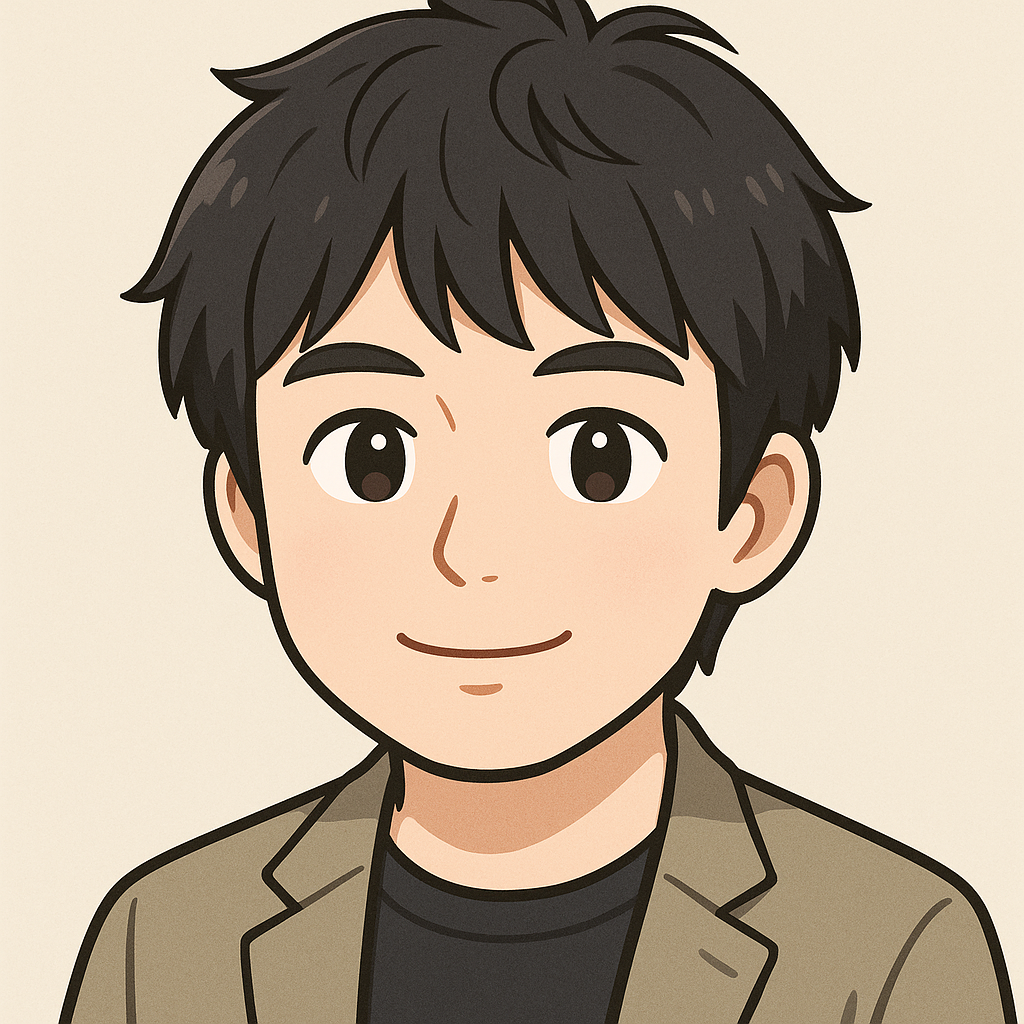
この記事の監修者:うしまる
北海道の元農協職員。15年以上、肉用牛農家の経営支援
ファイナンス設計・新規事業立ち上げを経験。
現在は「牛肉会」の編集長として、科学的かつ実務に基づいた牛肉情報を発信中。
ハラミは脂が多いって本当?
ハラミは見た目は赤身寄りでも、「噛んだ瞬間に脂の旨みを感じやすい部位」です。
ただしカルビのように外観から明らかな脂身が厚く付くタイプとは異なり、筋繊維の間(筋間)や筋肉内部(筋内)に細かく脂が入りやすいため、赤身に見えても口当たりはジューシーに感じます。
しかしながら、一般的なカルビやサーロインといった脂の入った部位よりも
ハラミの定義(横隔膜の一部で赤身寄りのホルモン部位)
- 部位の位置:ハラミは横隔膜(おうかくまく)周辺の筋肉で、焼肉分類ではホルモン(内臓系)に含まれますが、食感や味は赤身肉に近いのが特徴です。
- 呼称の違い:日本の焼肉店では「ハラミ」と総称されがちですが、肋骨側の薄い帯状の筋肉(いわゆるアウトサイドスカート)と、横隔膜中央部に垂れ下がるサガリ(ハンギングテンダー)を区別する場合もあります。どちらも共通して繊維が荒めで旨みが濃いのが持ち味です。
- 味の方向性:赤身寄りのコクに、脂の香りと甘みがじゅわっと広がるため、タレ・塩どちらでも満足度が高い部位です。
脂肪交雑(サシ)の入り方は個体差が大きい
- 品種・等級差:黒毛和種などはサシ(脂肪交雑)が入りやすく、同じハラミでもBMS(霜降り等級)や枝肉等級によって脂の入り方が大きく異なります。
- 飼養条件:肥育日数、飼料設計、性別(去勢・雌)などで脂質量と質(融点・風味)が変動します。
- トリミングの差:仕入れや下処理で周縁の脂や銀皮(膜)の取り方が異なると、見た目・噛み心地・脂感が大きく変わります。
- 輸入・国産の違い:カット規格や凍結・解凍履歴によっても脂の溶け方や口溶けに差が出ます。
「見た目は赤身でも実は脂が多い」と感じる理由
- 脂は“点在型”で見えにくい:カルビのように外層に白い脂身が厚く付くタイプではなく、細かい脂が筋繊維の間に散在。見た目は赤身でも、噛むと内部の脂が体温と加熱で溶けてにじみ出るためジューシーに感じます。
- 繊維構造とカット厚:ハラミは繊維がやや粗く保油性が高いため、厚切りにすると脂のコクと旨みがダイレクトに伝わります。逆に薄切りだと脂が落ちやすく、軽い食感になります。
- 焼き方の影響:強火の直火で表面を素早く焼くと余分な脂は落ち、内部の脂は閉じ込められるため、外は香ばしく中はジューシーというコントラストが強まり、脂が多く感じられます。
- タレとの相乗効果:甘口タレやコクのある味付けは、脂の甘みを強調します。塩・レモン・わさび醤油などに変えると、同じ脂量でも軽やかに感じることがあります。
- 温度と口溶け:和牛系の脂は融点が低めのことが多く、口中で素早く溶けて“脂感”を過敏に知覚しやすい点も「脂が多い」と感じる要因です。
このように、ハラミは“赤身の見た目”と“口当たりのジューシーさ”が共存する部位です。次章では、日本食品標準成分表(八訂)のデータを踏まえて、ハラミの脂質量・カロリーを他部位と定量比較し、実際どの程度「脂が多い」のかを数字で明らかにします。
ハラミの栄養価と脂質量を他の部位と比較
日本食品標準成分表2023(八訂)には「横隔膜(ハラミ)」の直接データはありませんが、参考値を加えた比較を行うと、ハラミの位置づけがよく分かります。
| 部位 | エネルギー(kcal) | 脂質(g) |
|---|---|---|
| カルビ(ばら 脂身つき) | 472 | 50.0 |
| リブロース(脂身つき) | 514 | 56.5 |
| サーロイン(脂身つき) | 460 | 47.5 |
| ハラミ(参考値・実測) | 約300〜350 | 約20〜25 |
| ヒレ(赤肉) | 207 | 15.0 |
| モモ(脂身つき) | 235〜244 | 18.7〜20.0 |
※カルビ・ロース・サーロイン・ヒレ・モモは 日本食品標準成分表2023(八訂) より。ハラミは公的データ未収録のため、食肉業界資料と流通データを参考にしています。
脂を活かす!ハラミの美味しい食べ方
- ✔ 表面を強火で焼き、脂を落としながら旨味を閉じ込める
網やフライパンをしっかり予熱し、片面を強火で短時間(30〜60秒)で焼き付けてから裏返す。高温で表面を固めることで、余分な脂は落ち、旨味は内部にキープされます。 - ✔ 焼きすぎは厳禁。ミディアム程度がベスト
ハラミは繊維がやや粗く焼き過ぎると脂が抜けてパサつきやすい部位。中心に軽く弾力が残るミディアムを目安に、焼いた後は30秒ほど休ませると肉汁が安定します。 - ✔ 脂をさっぱり食べる味付け
濃い甘口タレは脂の甘みを増幅。軽やかに食べたい場合は、塩+レモン・わさび醤油・大根おろしポン酢が好相性。薬味の辛味や酸味が脂のコクを引き締め、後味すっきりに。
ダイエット中にハラミを選ぶポイント
- ✔ 脂を落とす焼き方
脂が落ちやすい網焼き/グリルを選択。フライパンの場合は焼き面の脂をキッチンペーパーで都度オフし、周縁の脂身や銀皮は下処理で軽くトリミングすると脂質を抑えられます。 - ✔ 野菜やスープと組み合わせてバランスよく
食物繊維の多い葉野菜・キムチ・わかめスープを合わせ、脂の吸収をゆるやかに。ご飯は少量(茶碗半分)にし、たんぱく質中心の献立に調整します。 - ✔ 量の目安とカロリー感覚
1食あたりの目安は100〜120g。ハラミは公的成分表(八訂)に直接の掲載がないため参考値ですが、100gあたり約300〜350kcalを目安に計画すると無理なく調整できます。
※部位別の公的データは 日本食品標準成分表2023(八訂) を参照。
※ハラミ(横隔膜)は八訂に未収録のため、上記カロリーは一般流通データ等を踏まえた参考値です。
まとめ|ハラミは「赤身と脂のバランス型」の万能部位
- ✔ 見た目と実際の違い:
ハラミは赤身に見えますが、筋繊維の間に脂が入り込み、噛むとジューシーな旨味が広がります。 - ✔ 脂質量の位置づけ:
カルビやサーロインより脂は控えめで、モモやヒレよりは多い。中間的な栄養バランスを持つ部位です。 - ✔ 食べ方の工夫:
強火で表面を焼きつけて旨味を閉じ込め、ミディアムで仕上げるのがベスト。さっぱりした調味料とも好相性です。 - ✔ ダイエット対応:
脂を落とす網焼きやグリルを選び、100gあたり約300〜350kcalを目安にすれば安心して楽しめます。 - ✔ 総合評価:
ハラミは赤身の食べやすさと脂の旨味を両立した、焼肉で万能に活用できる部位。ダイエット中からグルメ志向まで幅広く支持されています。
関連記事
カルビ・ロース・ハラミの脂の違い・多さを徹底比較|栄養・カロリー・おすすめの食べ方
焼肉の定番3部位を脂質・味わい・栄養価で比較。好みに合った部位選びの参考にどうぞ。
サーロインとリブロースのカロリー比較|ダイエット中の選び方
高カロリーな高級部位のサーロインとリブロースを徹底比較。食べ方の工夫も紹介。
牛肉のメスとオスの違いとは?味・脂の入り方・柔らかさを比較
性別による肉質や脂の差を解説。ハラミの脂感を理解するヒントにもなります。
松阪牛と神戸牛の違いとは?日本を代表するブランド牛を比較
ブランド牛ごとの特徴や脂の質の違いを徹底解説。脂の美味しさを楽しみたい方におすすめ。
あなたにぴったりの牛肉がわかる「LINE診断」
「どの部位を選べばいいか分からない…」「贈り物にぴったりなお肉を知りたい!」
そんな方のために、牛肉会ではLINE限定の
かんたん診断コンテンツをご用意しました。
簡単な質問に答えるだけで、 あなたに合ったおすすめの牛肉が分かります。
- 自分や家族の「好み」に合わせて最適な部位を提案
- 「焼肉・すき焼き・ステーキ」など用途別にも診断OK
- 所要時間は30秒ほど、すぐに結果が届く
※友だち追加後すぐに診断できます。