【徹底比較】牛肉と豚肉どっちが体にいい?栄養・カロリー・健康効果を解説

健康やダイエットを意識するとき、牛肉と豚肉のどちらを選ぶべきか迷う人は多いでしょう。
特に、カロリーや脂質が気になったり、筋トレや貧血対策など目的に合わせて「どっちが体にいいのか」を知りたいという方は少なくありません。
結論から言うと、牛肉と豚肉はどちらも健康に役立つ食品ですが、目的によっておすすめは変わります。
牛肉は鉄分・亜鉛が豊富で筋トレや貧血予防に向いており、豚肉はビタミンB1が豊富で疲労回復や生活習慣病予防に効果的です。
本記事では、牛肉と豚肉の栄養素・健康効果の違い、体にいい食べ方や部位の選び方まで徹底解説します。
これを読めば、あなたの目的に合った正しい肉の選び方がわかります。
この記事でわかること
- ✅ 牛肉と豚肉のカロリー・脂質・タンパク質の違い
- ✅ ダイエット・筋トレ・健康に適した肉の選び方
- ✅ 牛肉と豚肉の栄養効果(鉄分・ビタミン・疲労回復)
- ✅ 体に良い食べ方・部位の選び方と注意点
- ✅ 牛肉と豚肉を使った健康レシピのヒント
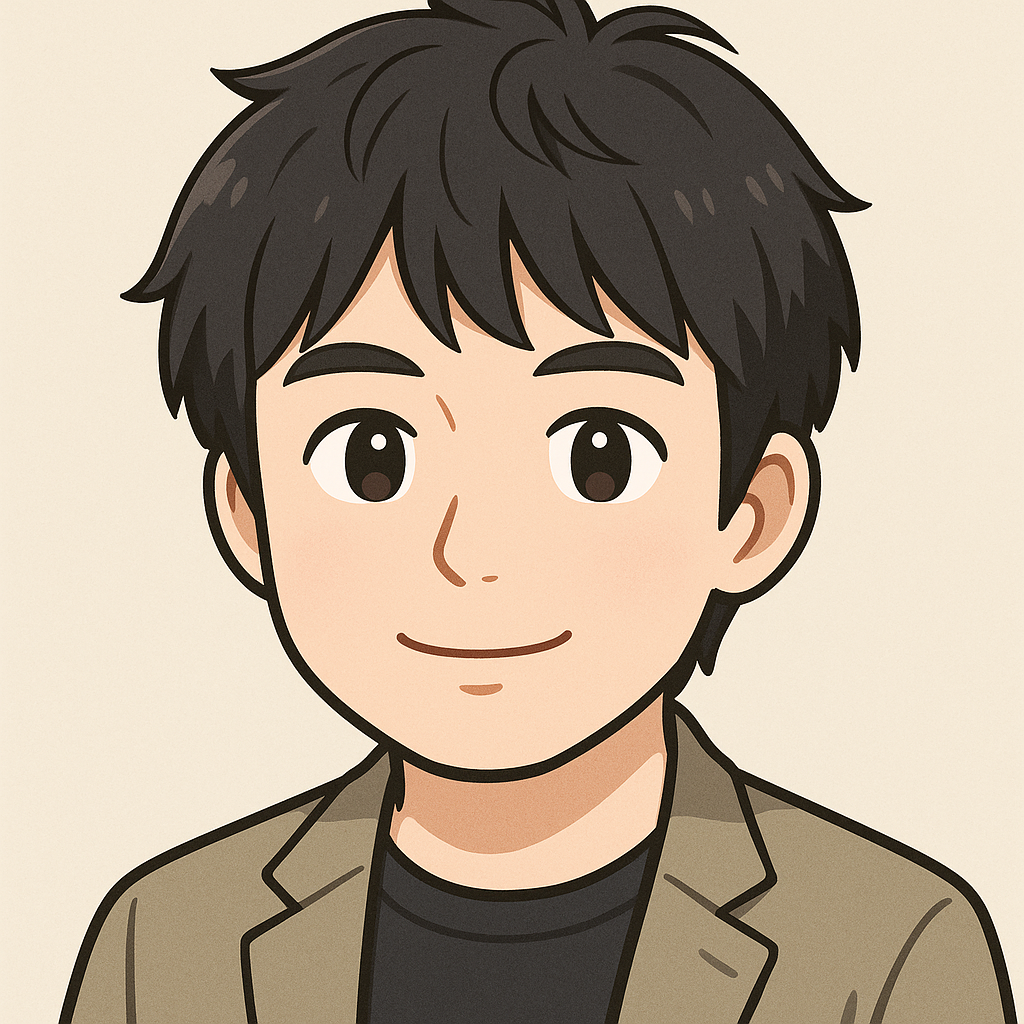
この記事の監修者:うしまる
北海道の元農協職員。15年以上、肉用牛農家の経営支援
ファイナンス設計・新規事業立ち上げを経験。
現在は「牛肉会」の編集長として、科学的かつ実務に基づいた牛肉情報を発信中。
結論:目的別に選ぶのが正解
牛肉と豚肉、どちらも体に良い栄養素を多く含んでいますが、目的によっておすすめは変わります。
牛肉は「貧血予防・筋力アップ」に優れる
牛肉には、吸収率の高いヘム鉄や筋肉の合成を助ける亜鉛が豊富です。
特に赤身のもも肉やヒレ肉は低脂質でタンパク質も多く、筋トレやダイエット中にもおすすめです。
豚肉は「疲労回復・生活習慣病予防」に有利
豚肉には、糖質の代謝や疲労回復を助けるビタミンB1が牛肉の約10倍も含まれています。
夏バテ予防や日常の疲れ対策には、豚ロースやヒレ肉が適しています。
食べ方・部位で健康効果は変わる
どちらの肉も、脂身が多い部位や調理法によってカロリーや脂質が増加します。
健康を意識するなら、赤身中心の部位+脂を落とす調理法がポイントです。
牛肉と豚肉の栄養素を徹底比較
牛肉と豚肉は、同じ肉類でも含まれる栄養素に違いがあります。
特に注目すべきは、鉄分とビタミンB1の差です。
| 肉の種類 | 部位 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 鉄(mg) | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛肉(和牛) | もも(皮下脂肪なし) | 212 | 20.2 | 15.5 | 2.7 | 0.09 |
| 牛肉(和牛) | そともも(皮下脂肪なし) | 219 | 18.7 | 16.6 | 1.0 | 0.08 |
| 牛肉(乳用肥育) | もも(皮下脂肪なし) | 169 | 20.5 | 9.9 | 1.3 | 0.08 |
| 豚肉(大型種) | もも(皮下脂肪なし) | 138 | 21.5 | 6.0 | 0.7 | 0.94 |
| 豚肉(大型種) | ヒレ(赤肉・生) | 118 | 22.2 | 3.7 | 0.9 | 1.32 |
この表からわかるように、
-
牛肉は鉄分が豊富で貧血予防に最適
-
豚肉はビタミンB1が圧倒的に多く疲労回復に効果的
-
カロリーや脂質は、赤身なら豚肉の方が低め
となります。
牛肉と豚肉の健康効果の違い
牛肉と豚肉はどちらも良質なたんぱく質源ですが、含まれる栄養素によって得られる健康効果が異なります。
ここでは代表的な健康効果を3つに分けて解説します。
① 牛肉:貧血予防・筋力アップに効果的
牛肉には、吸収率の高いヘム鉄が多く含まれており、貧血予防に役立ちます。
特に女性や成長期の子どもは鉄不足になりやすく、牛赤身肉(もも・ヒレ)は日常的に取り入れたい食品です。
さらに、亜鉛やクレアチンも豊富で、筋肉の合成や持久力の維持に効果的です。
筋トレやスポーツをしている方には、牛ももやヒレを週2〜3回程度取り入れると良いでしょう。
② 豚肉:疲労回復・夏バテ防止に優れる
豚肉には、ビタミンB1が牛肉の約10倍含まれています。
ビタミンB1は糖質をエネルギーに変える代謝に必須で、疲労回復や夏バテ防止に役立ちます。
また、豚肉の脂肪は牛肉より融点が低く、消化吸収されやすいのも特徴です。
日常生活で疲れやすい人や、デスクワーク中心で運動量が少ない人には、豚ロースやヒレを使った料理がおすすめです。
③ 生活習慣病対策は部位と調理法がカギ
-
牛肉・豚肉ともに、脂身が多い部位は飽和脂肪酸が多く、食べすぎると動脈硬化や生活習慣病のリスクが上がる
-
健康を意識するなら、赤身中心+しゃぶしゃぶ・蒸し料理で脂を落とすのがポイント
特に牛バラや豚バラの脂身は高カロリーなので、普段は赤身中心、特別な日に霜降り肉というバランスが理想です。
体にいい食べ方・部位の選び方
牛肉と豚肉の栄養素を最大限に活かすには、部位選びと調理法が重要です。
同じ肉でも、脂質量や調理法によって健康効果は大きく変わります。
① 牛肉は「赤身中心」で鉄分を効率よく吸収
牛肉の赤身は、鉄分や亜鉛が豊富で低脂質。
特に以下の部位がおすすめです。
-
もも(内もも・外もも・ランプ)
-
ヒレ(フィレ)
ポイント
-
ビタミンCを含む食材(ピーマン、ブロッコリー、レモン)と一緒に食べると鉄の吸収率がアップ
-
焼きすぎると水分が抜けてパサつくので、レア〜ミディアムで短時間加熱がおすすめ
② 豚肉は「ヒレ・もも」で疲労回復と低カロリーを両立
豚肉は、ビタミンB1が豊富で疲労回復に最適ですが、脂質が多い部位もあります。
健康を意識するなら、以下の部位を選びましょう。
-
ヒレ(脂質が少なく高タンパク)
-
もも(適度な脂質で煮物・炒め物に向く)
ポイント
-
にんにく・玉ねぎ・長ねぎなどのアリシンと一緒に食べるとビタミンB1の吸収率が向上
-
しゃぶしゃぶ・蒸し料理・ゆで調理で余分な脂を落とすとさらにヘルシー
③ 健康的な調理法の基本
-
脂を落とす調理法:しゃぶしゃぶ、煮込み、蒸し料理
-
油を使わない焼き方:フライパンにクッキングシートを敷くと脂質カット
-
食べる頻度の目安:1食あたり100〜150g、週2〜3回を目安にすると健康的
目的別おすすめ(ダイエット・筋トレ・健康維持)
牛肉と豚肉は、目的に合わせて選ぶことで健康効果を最大化できます。
ここでは、ダイエット・筋トレ・健康維持の3つの目的別に、おすすめの部位と食べ方を紹介します。
① ダイエット中は「低脂質の赤身」がおすすめ
-
おすすめ部位:
-
牛肉 → ヒレ・もも
-
豚肉 → ヒレ・もも
-
-
ポイント:
-
赤身肉は低カロリーかつ高タンパクで、満腹感を得やすくダイエット向き
-
しゃぶしゃぶ・蒸し料理で余分な脂を落とすとさらにヘルシー
-
例:牛ももしゃぶしゃぶサラダ/豚ヒレと野菜の蒸し煮
② 筋トレ・筋力アップは「牛赤身+鉄分重視」
-
おすすめ部位:
-
牛肉 → もも・ランプ・ヒレ
-
補助的にレバーを加えると鉄分・ビタミンB群が強化
-
-
ポイント:
-
牛赤身は鉄分・亜鉛・クレアチンが豊富で筋肉合成をサポート
-
トレーニング後は、糖質(ご飯・パスタ)と一緒に食べると吸収効率UP
-
例:牛ヒレステーキ+玄米リゾット/牛ももとブロッコリー炒め
③ 健康維持・疲労回復は「豚肉+アリシン食材」
-
おすすめ部位:
-
豚肉 → ロース・ヒレ・もも
-
疲労回復を意識するならヒレが最適
-
-
ポイント:
-
ビタミンB1は糖質代謝を助け、慢性的な疲労やだるさの軽減に役立つ
-
にんにく・玉ねぎ・ニラなどアリシンを含む食材と組み合わせると効果倍増
-
例:豚ヒレと玉ねぎの生姜焼き/豚しゃぶとにんにくポン酢サラダ
まとめ
-
牛肉は鉄分・亜鉛が豊富で、貧血予防や筋力アップに向く
-
豚肉はビタミンB1が牛肉の約10倍で、疲労回復・生活習慣病予防に有効
-
健康を意識するなら、赤身中心+しゃぶしゃぶや蒸し料理で脂を落とすのがポイント
-
ダイエットは低脂質の赤身、筋トレは牛赤身、疲労回復は豚ヒレ・ももが最適
-
食べる量は1食100〜150g、週2〜3回程度が健康的で続けやすい





